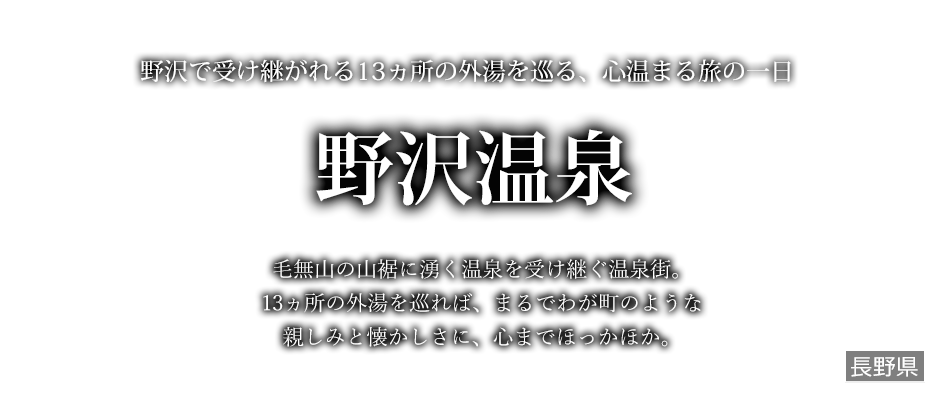野沢温泉の歴史と特徴

野沢温泉が発見された経緯については主に3つの説があります。ひとつは聖武天皇が国を治めていた時代の高僧・行基の小菅山巡行の際に見つけられたという説、そして修行中の山伏が見つけたという説、残るひとつが傷を負った熊を追いかけていた猟師が見つけたという説。鎌倉中期に「湯山村」として歴史上に登場し、以後20数軒の湯宿が並ぶ湯治場として知られてきました。
現在も村にはおよそ30の源泉が湧き出ており、無料で利用できるものを含め外湯が13ヵ所。麻釜(おがま)で野菜などを調理する昔ながらの暮らしは今なお受け継がれています。宿に着いたら早速外湯巡りへ。江戸時代から「湯仲間」によって営まれてきたという外湯は、すべて天然温泉かけ流し。徒歩圏にあり、山手の「滝の湯」から南の「中尾の湯」まででも歩いて20分ほど。湯船では地元の人たちと、気兼ねのない、まさしく「裸と裸のおつきあい」。そんな飾らない風景も、温泉を「村の財産」として守り続ける野沢温泉の醍醐味といえるでしょう。
野沢温泉のみどころ
 麻釜
麻釜
90度もの高温の温泉が湧き出る野沢温泉の源泉のひとつ。現在も、野菜をゆでたり、温泉たまごを作ったりするために、地元の人々に利用されている。野沢温泉を象徴するスポット。 |
 つつじ山公園・百番観音
つつじ山公園・百番観音
約5,000株のつつじが群生し、6月に見頃を迎える野沢温泉村指定名勝。百番観音は、西国三十三カ所、坂東三十三カ所、秩父三十四か所の観音霊場を合わせたもの。散策しながら巡るのもお奨め。 |
 おぼろ月夜の館
おぼろ月夜の館
「春が来た」「故郷」「朧月夜」などを作詞した国語・国文学者である高野辰之博士の功績を称えて作られた記念館。田中正秋、笠松紫浪、棟方志功の作品なども展示されている。 |
エリア:長野県 > 野沢温泉
-

- 2件中 (1~2件を表示)
-


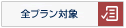
旅館さかや
野沢温泉
脈々と暖簾を受け継ぐこと十七代、野沢温泉の憧れの宿
料金目安18,000円~ 大人お一人さま 1泊2食付
アクセス
JR飯山線戸狩野沢温泉駅よりバスで約15分

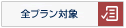
野沢グランドホテル
野沢温泉
地元の幸満載の「おごっつぉ料理」は心に沁みる懐かしき味
料金目安11,000円~ 大人お一人さま 1泊2食付
アクセス
JR飯山線戸狩野沢温泉駅よりバスで約20分
-

- 2件中 (1~2件を表示)
-