修善寺温泉の歴史と特徴

「修善寺」は平安時代に弘法大師が開いた寺の名。桂川の岩場にある修善寺温泉の象徴「独鈷(どっこ)の湯」は、弘法大師が独鈷(※煩悩を打ち砕くといわれる仏具)で岩を砕いて湧き出たといわれています。その弘法大師の開湯以来1200年、山深い自然に囲まれた地は源氏と北条氏の興亡があった鎌倉時代を経て、現在は古都の風情を感じさせる情緒溢れる温泉地として多くの人に愛されています。
四季折々の自然が美しい修善寺の町は、浴衣が似合います。なかでも青々とした竹林が清々しい「竹林の小径」は散策に最適。桂川沿いに敷かれた石畳を浴衣を着て歩けば、非日常の贅沢な気分が味わえます。虎渓橋を南に渡った先には、この地で暗殺された鎌倉二代将軍源頼家の冥福を祈って母・北条政子が建てたという指月殿。界隈には歩き疲れたときのひと休みにぴったりのおしゃれなカフェがあるのもうれしい限りです。
そして最後は修善寺の湯でゆっくり時を忘れてリラックス。伊豆最古の温泉は、肩ひじ張らずのんびり過ごすことの素敵さをあらためて感じさせてくれます。
修善寺温泉のみどころ
 修善寺
修善寺
大同2年(807年)に弘法大師が開創したといわれる名刹。1200年の時代の流れとともに、真言宗から臨済宗、曹洞宗と宗派も変遷している。 |
 独鈷の湯
独鈷の湯
修善寺温泉の発祥といわれる元泉源。現在は湯小屋と湯船だけが残されている。※入浴はできません |
 筥湯(はこゆ)
筥湯(はこゆ)
鎌倉二代将軍源頼家が入浴していた桧造りの湯を再現。温泉情緒が味わえる。 |
エリア:静岡県 > 修善寺温泉
-

- 1件中 (1~1件を表示)
-


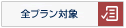
柳生の庄
修善寺温泉
清々しい緑濃き竹林に佇む数寄屋造りの宿にあるのは格別の愉悦・・・
料金目安44,000円~ 大人お一人さま 1泊2食付
アクセス
伊豆箱根鉄道駿豆線修善寺駅より車で約10分(修善寺温泉バス停より無料送迎あり/要予約)
-

- 1件中 (1~1件を表示)
-




